良い睡眠で、からだもこころも健康に
公開日:2023年02月17日
睡眠ガイド2023
日本人の平均睡眠時間は世界の中でも短く、国民一人ひとりの十分な睡眠の確保は、重要な健康課題になっています。
厚生労働省の「睡眠ガイド2023」は、休養・睡眠分野の取り組みをさらに推進するため、健康づくりに大きく関わる睡眠の特徴を国民にわかりやすく伝えることで、より多くの国民が良い睡眠を習慣的に維持するために必要な生活習慣を身につける手だてになることをめざし、策定されています。
睡眠と健康の関係(睡眠が悪化することで起こること)
- さまざまな疾患の発症リスクが増加し、寿命の短縮のリスクも高まる。
- 労働災害や自動車事故など、眠気や疲労が原因の事故や怪我のリスクが高まる。
- 心身の疲労回復する機能や、成長や記憶(学習)の定着・強化など環境への適応能力を向上させる機能も損なう。
睡眠は、健康増進・維持に不可欠な休養活動です。日常的に睡眠の質・量ともに十分な睡眠を確保することにより、心身の健康を保持し、生活の質を高めていくことが重要です。
良い睡眠をとるための推奨事項
1 . 成人
- 6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保する。(適正な睡眠時間には個人差があります)
- 食生活や運動などの生活習慣や、寝室の睡眠環境などを見直して、睡眠休養感(睡眠で休養がとれている感覚)を高める。
- 生活習慣などの改善を図っても、睡眠の不調や睡眠休養感の低下が長く続く場合は、病気が潜んでいる可能性にも留意する。
2 . 子ども
- 小学生は9から12時間、中学・高校生は8から10時間を参考に睡眠時間を確保する(下記参照)。
- 朝は太陽の光を浴びて、朝食をしっかりとり、日中は運動をして、夜更かしの習慣を避ける。
各年齢の睡眠時間の目安
- 1から2歳児:11から14時間
- 3から5歳児:10から13時間
- 小学生:9から12時間
- 中学・高校生:8から10時間
3 . 高齢者
- 長い床上時間(寝床に入っている時間)は健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安に、必要な睡眠時間を確保する。
- 食生活や運動などの生活習慣、寝室の睡眠環境などを見直して、睡眠休養感を高める。
- 長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中の長時間の昼寝は避け、活動的に過ごす。
良質な睡眠のための環境づくり
1 . 光の環境
- 朝目覚めたら部屋に朝日を取り入れ、日中にできるだけ日光を浴びる。
- 寝室にはスマートフォンやタブレット端末を持ち込まず、できるだけ暗くして寝る。
日中に多くの光を浴びることで、夜間のメラトニン(睡眠を促すホルモン)分泌量が増加し、体内時計が調整され、入眠の促進につながります。夜間に照明やスマートフォンの強い光を浴びると、メラトニンの分泌が抑制されてしまい、入眠が妨げられてしまいます。
高齢者は夜間にトイレへ行くことも多いため、転倒しないように間接照明や足元灯を利用し、眼に入る光量を減らす工夫が必要です。
2 . 温度の環境
- 夏の寝室はエアコンを用いて涼しく維持する。
- 冬の室温は18度以上に維持し、就寝前にもできるだけ温かい部屋で過ごす。
- 就寝の約1から2時間前に入浴し、体を温めてから寝床に入る。
人の深部体温は日中の覚醒時に上昇し、夜間の睡眠時に低下します。就寝前に手足の皮膚の血流が増加することで、体温が外に放散され、深部体温が下がり始めると、入眠しやすい状態になります。
就寝約1から2時間前の入浴は、手足の血管を拡張することによって熱の放散を促進し、入眠を促す効果が期待できます。しかし、極端に湯の温度が高いと交感神経の活動が亢進し、かえって入眠を妨げてしまうので注意が必要です。
3 . 音の環境
- できるだけ静かな環境で、リラックスできる寝衣・寝具で眠る。
屋外の音が気になる場合は、カーテンを防音のものにする、寝床の位置をできるだけ窓から遠くに移動させるなどして、静かな環境を作りましょう。
睡眠と生活習慣(運動や食事など)
適度な運動習慣を身につける
日中にからだをしっかり動かすことは、入眠の促進や中途覚醒の減少を促し、睡眠時間の増加と睡眠の質向上に役立ちます。
しっかり朝食をとる
朝食をとることで、体内時計が調整され、睡眠・覚醒リズムが整います。
就寝前の夜食や間食は控える
就寝前の夜食や間食は、体内時計を後退させ、睡眠休養感を低下させてしまします。
味の濃いものや、塩分が高い食べ物は控える
日中に過剰摂取した塩分は、睡眠中に排泄されるため、夜間の排尿回数が増えてしまいます。
就寝前にリラックスする時間を設ける
スムーズに入眠するためには、脳の興奮を鎮めることが大切です。そのためには少なくとも就寝前1時間はリラックスする時間を確保することが効果的です。
無理に寝ようとすることを避け、眠気が訪れてから寝床に入る
眠気が訪れていないにもかかわらず、無理に眠ろうとすると、寝付けないことを必要以上に悩んだり、悩み事を寝床に持ち込んでしまい、余計に寝付けなくなってしまいます。そんな時は、いったん寝床を離れ、寝床以外のリラックスできる場所で、眠気が訪れるまでに安静にして過ごし、眠気が訪れてから寝床に入ると効果的です。
規則正しい生活習慣により、日中の活動と夜間の睡眠のメリハリをつける
規則正しい生活は、睡眠の質を高め、日中の眠気を改善します。
睡眠と嗜好品
日常生活の中で、習慣的に摂取する嗜好品の中には、睡眠に影響を及ぼすものがあります。心身のリラクゼーションは、良い睡眠をとるために重要な要素ですが、嗜好品は使用量や使用時刻(タイミング)を誤ると睡眠を悪化させ、健康に有害な場合があるので、注意が必要です。
1 . カフェイン
- カフェインの摂取量は1日400mg(注1参照)を超えないようにする
- カフェインの夕方以降の摂取は控える
カフェインは覚醒作用を有します。
カフェインの代謝には個人差がありますが、血液中の濃度や代謝に要する時間などを考慮した結果、1日に400mgを超えるカフェインの摂取や、夕方以降のカフェイン摂取は、睡眠に悪影響を与える可能性があります。
(注1)カフェイン400mgとは、ドリップコーヒーでコーヒーカップ4杯分(700ml)、市販のペットボトルコーヒーで1.5本分(750ml)に含まれる量。
(注2)エナジードリンクには、コーヒーの5倍近いカフェインを含有するものもあります。
2 . アルコール
- 晩酌は控えめにし、寝酒はしない
アルコールは一時的に寝付きを促進し、睡眠前半では深い睡眠を増加させます。しかし、睡眠後半の眠りの質は悪化し、飲酒量が増加するにつれて中途覚醒回数が増加してしまいます。
3 . ニコチン(喫煙)
- 禁煙を目指しましょう
たばこに含まれるニコチンは覚醒作用を有しており、寝つきの悪化、中途覚醒の増加等の睡眠への悪影響をもたらします。ニコチンの血中半減期は約2時間であり、夕方の喫煙であっても、眠る前までその作用が残存することがあります。
より詳しく知りたい人は、冒頭に掲載しているリンク「厚生労働省 睡眠ガイド2023」を確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉センター 健康福祉課(健康づくり担当)へのお問い合わせ
〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目3-1
電話番号:092-962-5151
メールフォームによるお問い合わせ






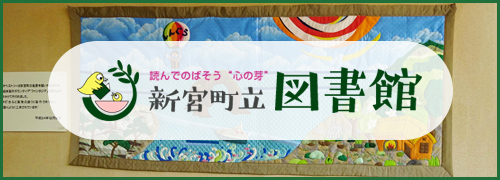




更新日:2025年04月01日