熱中症にご注意ください
公開日:2023年02月20日
熱中症は、気温と湿度が上がり始める5月から6月ごろから起こりやすくなるため、注意が必要です。
熱中症の予防には、水分補給と暑さを避けることが有効です。また、屋外だけでなく、暑さを感じにくい室内でも熱中症予防は大切です。
熱中症はどのようにして起こるのか
熱中症を引き起こす条件は「環境」「からだ」「行動」によるものが考えられています。
【環境】気温や湿度の高さ、日差しの強さ、風の弱さ、閉め切った室内、エアコンがないなど
【からだ】高齢者や子ども、持病がある、脱水状態(下痢など)、体調不良(寝不足や二日酔いを含む)など
【行動】激しい労働や運動、屋外での作業、こまめな水分補給をしていないなど
これら3つの要因によって、体温が上昇し、調整機能のバランスが崩れることで、身体に熱が溜まってしまいます。
このような状態が熱中症です。
熱中症の症状
めまい、立ちくらみ、生あくび、筋肉のこむら返り、大量の発汗
【症状がすすむと】頭痛、吐き気、嘔吐(おうと)、倦怠感、虚脱感、集中力や判断力の低下、いつもと様子が違う
【重症になると】返事がおかしい、意識喪失、けいれん、体が熱い
熱中症の予防方法
暑さを避けるためにできること
1. 扇風機やエアコンで温度をこまめに調節する
2. 遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用する
3. 外出時には日傘や帽子を着用する
4. 天気の良い日は日陰を利用し、こまめに休憩する
5. 熱中症警戒アラート発表時には外出をできるだけ控える
6. 吸湿性・速乾性のある通気性の良い衣服を着用する
7. 保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、体を冷やす
8. 室内でも、外出時でも、のどの渇きを感じていなくても、こまめに水分・塩分などを補給する
熱中症が疑われる人を見かけた時の対処法
- エアコンが効いている室内や、風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難させましょう
- 衣服をゆるめ、体を冷やしましょう(首回り、脇の下、足の付け根など)
- 水分・塩分、スポーツドリンク、経口補水液(下記参照)などを補給しましょう
こんな時は医療機関に!
熱中症を疑う症状があり、意識がない、または呼びかけに対する返答がおかしい場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
意識はあるが、水分を自力で摂れない場合は医療機関へ。
水分を自力で摂れ、必要な応急処置をおこなったものの、症状が改善しない場合も、医療機関へ行きましょう。
経口補水液の作り方
熱中症のような症状を認めた際には、特に塩分と水分が適切に配合された経口補水液が望ましいです。
経口補水液として市販されているものもあるので、急な熱中症の症状に備えて常備しておくと良いでしょう。
作り方
- 砂糖40グラム(上白糖大さじ4と1/2杯)と食塩2グラム(小さじ1/2杯)を1リットルの水によく溶かす。
- 果汁(レモンやグレープフルーツなど)を絞ると飲みやすくなります。
(注1)飲みすぎると塩分や糖分の摂りすぎになります。注意してください。
(注2)心臓や腎臓などの治療中で、医師より水分の摂取について指示がある場合は、その指示に従ってください。
高齢者や子ども、障がいがある人は、特に注意が必要です!
熱中症患者のおよそ半数は65歳以上の高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能や、暑さに対するからだの調整機能が低下しているので、注意が必要です。
また、子どもは体温の調整能力がまだ十分に発達していないので、気を配る必要があります。
障がいのある人も、体温調節が難しい場合や、自分で水分を摂れない、自ら症状を訴えられない場合があるため、配慮しましょう。
熱中症対策(高齢者向け)チラシ (PDFファイル: 511.1KB)
バランスの良い食事と十分な睡眠をとることも大切です。
熱中症は、その日の体調や暑さに対する慣れなども影響します。バランスの良い食事や十分な睡眠をとり、体調の変化に十分に気をつけましょう。
そして、無理をせず、徐々にからだを暑さに慣らしましょう。
また、熱中症について正しい知識を身につけ、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
福祉センター 健康福祉課(健康づくり担当)へのお問い合わせ
〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜四丁目3-1
電話番号:092-962-5151
メールフォームによるお問い合わせ






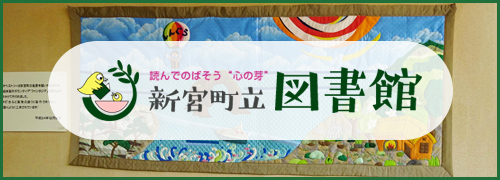




更新日:2025年05月08日